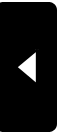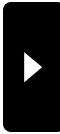2018年08月08日 17:45
手に馴染む≫
カテゴリー
今年の夏は殺人的に暑いですね
毎日天気予報で40度越えたって
暑くてもやらなきゃいけないのが仕事です

鉋の刃(裏側)、写真だと分かりにくいですが
長く使っていると刃先の平らな部分(光っている部分)がなくなってしまいます。
大工の間では(裏が無くなる)と言い
このままだと使用できないので、砥石や
裏打ちを使って裏側を平らにしあげます。

写真だと変わらない様にみえますが、約6ミリ
程平らになっています。
後は刃先を研いで削るだけ✨

こんなに鉋グズが出ました
やっぱり昔から使っている手道具は
手に馴染み、仕事もはかどりますね。
毎日天気予報で40度越えたって
暑くてもやらなきゃいけないのが仕事です

鉋の刃(裏側)、写真だと分かりにくいですが
長く使っていると刃先の平らな部分(光っている部分)がなくなってしまいます。
大工の間では(裏が無くなる)と言い
このままだと使用できないので、砥石や
裏打ちを使って裏側を平らにしあげます。

写真だと変わらない様にみえますが、約6ミリ
程平らになっています。
後は刃先を研いで削るだけ✨

こんなに鉋グズが出ました
やっぱり昔から使っている手道具は
手に馴染み、仕事もはかどりますね。
2018年08月01日 10:42

自然乾燥の柱は、この様に背割れがはいってます。
この背割れが入っている事で、3面の表面に割れが
入らないようになります。
ただ、この背割れが案外厄介者なんです。
柱のホゾ(柱が土台や梁に刺さる部分)を造る時に、そのまま造ってしまうと殆ど形がなくなってしまいます。
そこで

くさびを造って


木工ボンドを付けてはめ込みます。

こうやって埋め仕事も、建物が完成した時には
見えなくなってしまいます。
今じゃほとんど見られない仕事ですが、
無駄な仕事じゃないとおもいますね。
見えない仕事≫
カテゴリー

自然乾燥の柱は、この様に背割れがはいってます。
この背割れが入っている事で、3面の表面に割れが
入らないようになります。
ただ、この背割れが案外厄介者なんです。
柱のホゾ(柱が土台や梁に刺さる部分)を造る時に、そのまま造ってしまうと殆ど形がなくなってしまいます。
そこで

くさびを造って


木工ボンドを付けてはめ込みます。

こうやって埋め仕事も、建物が完成した時には
見えなくなってしまいます。
今じゃほとんど見られない仕事ですが、
無駄な仕事じゃないとおもいますね。
2018年06月22日 19:00
割れちゃった≫
カテゴリー
墨付けの時は割れてなかったのに
刻もうとしたら割れてました
しかも、結構ひどく

この部材(手前側)は軒先を支えるので、
これ以上割れたら困ります。
そんな時は

クリの木で造った蝶々
この蝶々を

割れてる所に置いて、鉛筆で写し
後は掘るだけ

掘れたら蝶々をはめて完成です。

こんな作業も楽しいです
今日も1日お疲れ様でした
刻もうとしたら割れてました
しかも、結構ひどく

この部材(手前側)は軒先を支えるので、
これ以上割れたら困ります。
そんな時は

クリの木で造った蝶々
この蝶々を

割れてる所に置いて、鉛筆で写し
後は掘るだけ

掘れたら蝶々をはめて完成です。

こんな作業も楽しいです
今日も1日お疲れ様でした
2018年06月05日 21:25



本日、Y様邸の地鎮祭が執り行われました。
雨男の自分なのですが、気持ちよく晴れて
くれました。
地鎮祭は自分も緊張しますし、お施主様にとって
一生に一回の祭事なので いつもより口数が
少ないですね。
その後工場にもどり刻み加工になりました。
刻み加工も中盤に入り、部材が小さいものも
出来たきたので削り仕上げは(超仕上げ)機械に
頼ってみました。
さすがに使い古した刃物から、目立てた(研ぎだした)
刃物に交換します。
昔、この作業で痛い思いをしたので緊張します。


刃物を機械にセットし、早速削ってみます。


削り屑の厚みも調子良く

あっという間に作業が終わりました。

タケノコ模様の所は仕上げてなく、柾目(筋状)
の所は仕上げてあります。
ただ、良くみてみるとダメですね。
艶がないです。
明日は手で(鉋かけ)から始めないと…
今日も1日お疲れ様でした。
地鎮祭≫
カテゴリー



本日、Y様邸の地鎮祭が執り行われました。
雨男の自分なのですが、気持ちよく晴れて
くれました。
地鎮祭は自分も緊張しますし、お施主様にとって
一生に一回の祭事なので いつもより口数が
少ないですね。
その後工場にもどり刻み加工になりました。
刻み加工も中盤に入り、部材が小さいものも
出来たきたので削り仕上げは(超仕上げ)機械に
頼ってみました。
さすがに使い古した刃物から、目立てた(研ぎだした)
刃物に交換します。
昔、この作業で痛い思いをしたので緊張します。


刃物を機械にセットし、早速削ってみます。


削り屑の厚みも調子良く

あっという間に作業が終わりました。

タケノコ模様の所は仕上げてなく、柾目(筋状)
の所は仕上げてあります。
ただ、良くみてみるとダメですね。
艶がないです。
明日は手で(鉋かけ)から始めないと…
今日も1日お疲れ様でした。
2018年05月26日 19:01

相変わらず、刻み加工が続いています。
さすがに120本もあると、なかなか終わらないですね。
刻み終わった部材は、鉋をかけてツルツルに
しあげます。

刻み加工をやらせてもらえる事に感謝し、
まだまだ頑張って行こうと思います。
皆さん、1週間お疲れ様でした。
まだまだ手刻み作業≫
カテゴリー

相変わらず、刻み加工が続いています。
さすがに120本もあると、なかなか終わらないですね。
刻み終わった部材は、鉋をかけてツルツルに
しあげます。

刻み加工をやらせてもらえる事に感謝し、
まだまだ頑張って行こうと思います。
皆さん、1週間お疲れ様でした。
2018年05月23日 15:39

お手伝いに出向いた現場で、桧を伐採していたので
少し枝を頂戴しました。
はじめは、埋め木用にと思っていたのですが、
なんか皮を剥きたくなったので、剥いてみたら

ひょっとして乾燥させたら、手摺になるんじゃないかい?
後は、乾燥させてからのお楽しみ。
それにしても、綺麗に剥けました。
皮も使えるかな?
アイデア次第?≫
カテゴリー

お手伝いに出向いた現場で、桧を伐採していたので
少し枝を頂戴しました。
はじめは、埋め木用にと思っていたのですが、
なんか皮を剥きたくなったので、剥いてみたら

ひょっとして乾燥させたら、手摺になるんじゃないかい?
後は、乾燥させてからのお楽しみ。
それにしても、綺麗に剥けました。
皮も使えるかな?
2018年05月14日 15:32

昨日、豊橋のテーブル工房 むくの木 さんで
月一がらくた市が行われていたので、
遊びに行って来ました。
普段、杉や桧、松を使っていますが、
ここでは トチやナラ、クリ、カバ、クルミ
などがあり、削ったらどんな表情に
なるか楽しみです。

お宝発見≫
カテゴリー

昨日、豊橋のテーブル工房 むくの木 さんで
月一がらくた市が行われていたので、
遊びに行って来ました。
普段、杉や桧、松を使っていますが、
ここでは トチやナラ、クリ、カバ、クルミ
などがあり、削ったらどんな表情に
なるか楽しみです。

2018年05月10日 09:53

昨日は、木遊舎で小さな小屋製作
でした。
朝まで降っていた雨も止み、1日
楽しく作業ができました。


外壁には板を張り、無塗装仕上げで
時間と共に味わいのある変化を、
楽しめると思います。
その後、三方原の古民家を見せていただき
、その美しさに感動しました。



やっぱり、土壁は良いですね。
小屋≫
カテゴリー

昨日は、木遊舎で小さな小屋製作
でした。
朝まで降っていた雨も止み、1日
楽しく作業ができました。


外壁には板を張り、無塗装仕上げで
時間と共に味わいのある変化を、
楽しめると思います。
その後、三方原の古民家を見せていただき
、その美しさに感動しました。



やっぱり、土壁は良いですね。